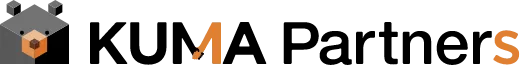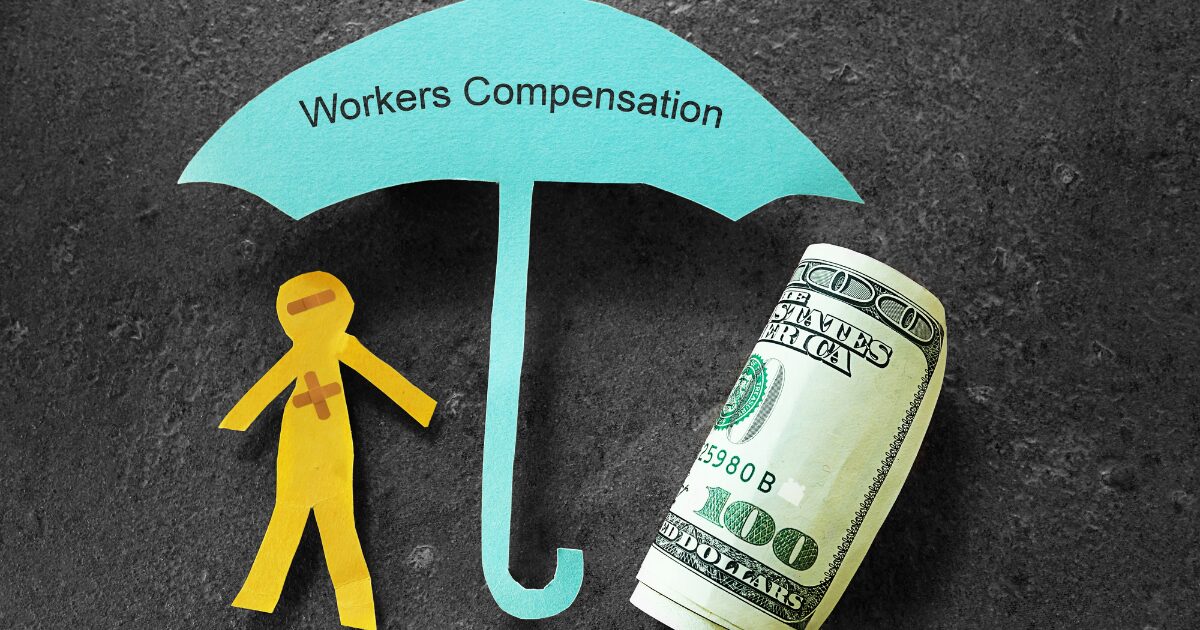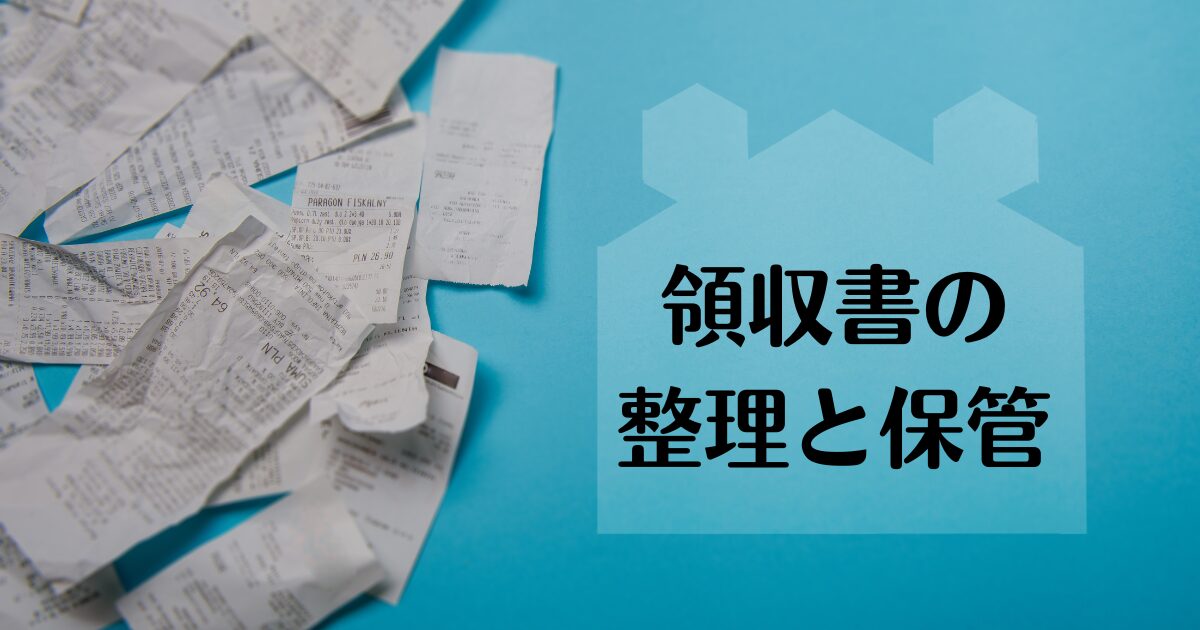請求書の発行と管理
今回は「請求書の発行と管理」についてお話しします。
一見地味なテーマに思えるかもしれませんが、
すべての事業者にとって非常に重要な内容です。
ぜひ最後までお付き合いください!
まず、請求書の保管がなぜ必要なのかについて。
事業者の皆さんが請求書を発行する側の立場で考えてみてください。
もちろん、ビジネス取引上、請求書は「この内容でお金を払ってくださいね」という意味でやり取りされますが、それだけではありません。
受け取った側にとって請求書は「経費の証拠」となるため、法人税法や消費税法の観点から保管義務があります。
日付やインボイス番号の記載が求められるのは、主に消費税法の要件です。
ちなみに法人税法では「メモでもOK」とされていることがあります。
たとえば、お客様と会食したけれど領収書をもらい忘れた場合でも、「何月何日に誰とどこに行って、いくらかかった」とメモしておけば大丈夫です。しかし、消費税法上ではそうはいきません。
適切な記載がされた請求書がないと、仕入税額控除ができなくなるのです。
では、どんな記載が必要なのか?
インボイス制度で求められる6つの項目を押さえておきましょう
- 発行者の氏名・名称と登録番号(インボイス登録事業者の場合)
- 取引年月日
- 取引内容(商品やサービスの名称など)
- 税抜金額または税込金額
- 適用税率ごとの消費税額
- 取引先の氏名・名称
特に「税率ごとに分けて記載する」点が大切です。
たとえば、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の商品が混在する場合、それぞれの金額と税額を明確に分けて書く必要があります。
なお、飲食店やスーパーなど不特定多数の相手に請求する場合、6番の「相手先の氏名・名称」の記載は省略が認められています。宛名が書けない事情がある業種への配慮です。
次に、「不備があった場合どうするか?」についてですが、原則として請求書は再発行が必要です。記載ミスがあると、受け取った側が仕入税額控除を受けられない恐れがあるため、再発行によって信頼関係を守る姿勢が重要です。
では、ミスを防ぐためにどうすれば良いか?
おすすめは会計ソフトの導入です。最新のインボイス対応フォーマットを自動で生成してくれるだけでなく、
売上の自動記帳や請求書のメール送信・クラウド保管など、多機能でとても便利です。
電子帳簿保存法にも対応しているソフトなら、印刷・郵送不要で、そのまま法的に正しい形で保存ができます。こうしたツールを活用することで、事務作業の効率化とミスの削減が同時に実現できます。
最後にまとめです:
- 請求書には6つの記載事項が必要です。
- 不備があった場合には再発行が求められます。
- 会計ソフトを導入すると、作成・保管・送付まで効率的になります。
請求書はあなたのビジネスの「信頼」を表す大事な書類です。ぜひ、ミスのない運用体制を整えていきましょう。
今回の解説が少しでもお役に立てば嬉しいです。