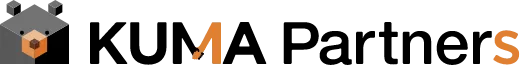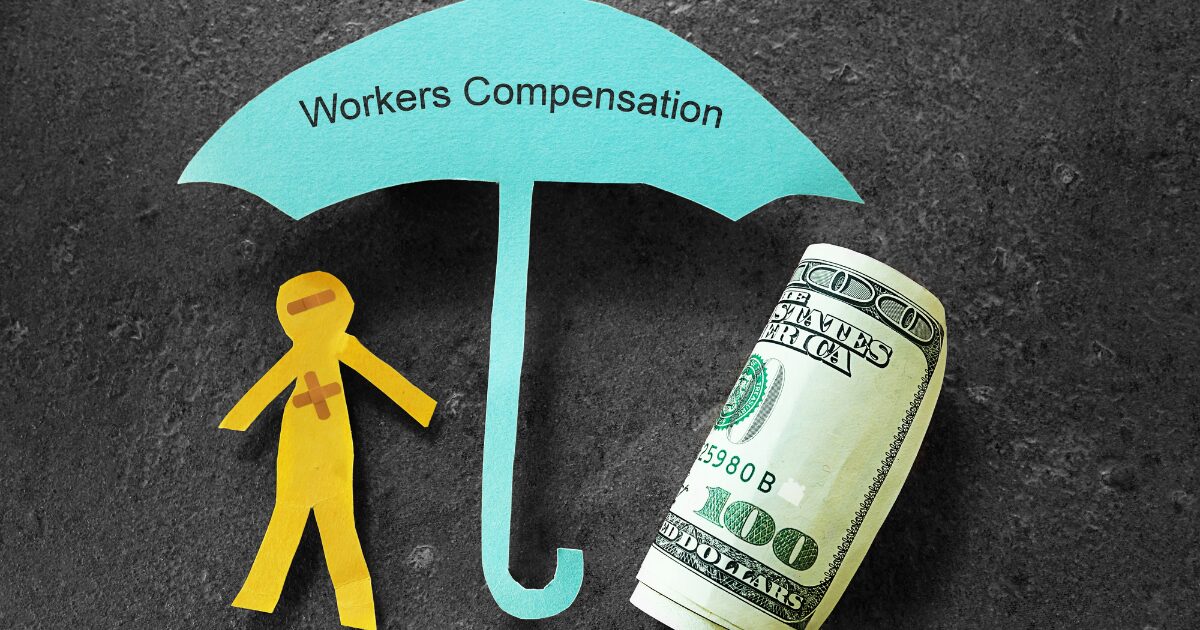領収書の整理と保管
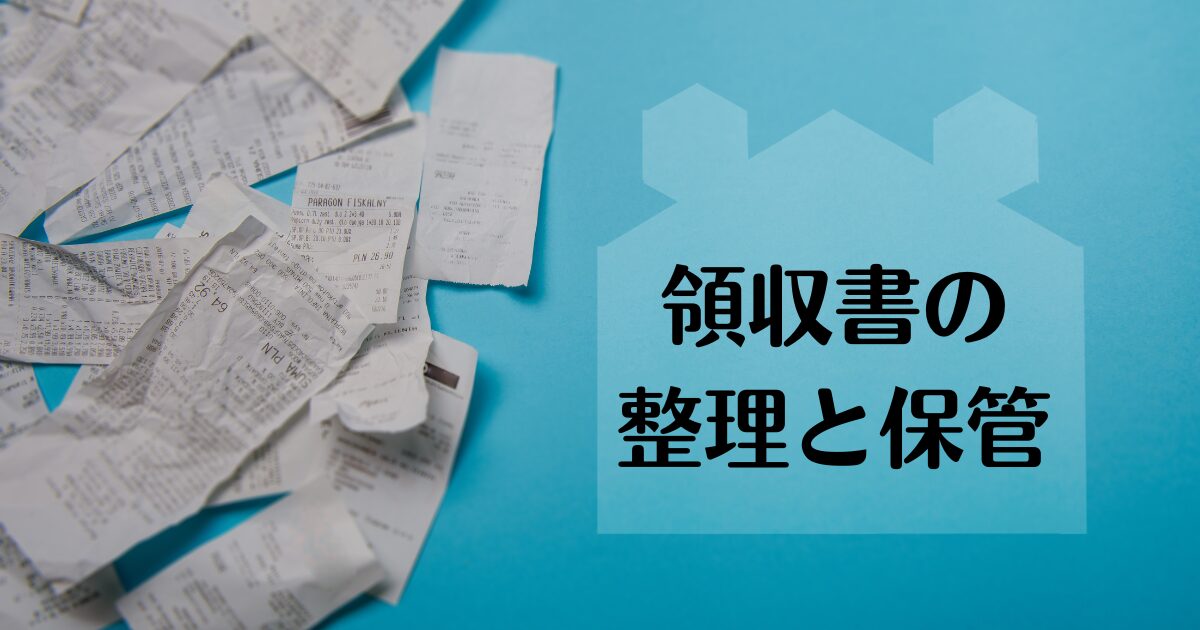
日々の業務に欠かせない「領収書」。つい“なんとなく”保管してしまいがちですが、
実はルールを守っていないと大きなリスクにつながることも。
今回は、フリーランスや個人事業主の方が知っておきたい「領収書の整理と保管」について、税務の観点からわかりやすく解説します。
1. 領収書の保管期間は原則7年
「何年保管すればいいの?」という疑問に対して、答えは 原則7年間の保管が必要です。
これは、税務調査で遡って確認される最大の期間に対応するためです。もし領収書がないと、経費として認められない可能性があるため、しっかりと保管しておきましょう。
例外もあります:
- 白色申告の方は5年
- 赤字決算の年度は10年保管が推奨(繰越欠損金を適用するため)
将来的に青色申告へ切り替える場合なども考慮し、基本は“7年保管”をおすすめします。
2. 電子帳簿保存法とは?
近年の法改正で「電子帳簿保存法」が整備され、電子データは電子のままで保管することが求められるようになりました。
保存区分の考え方:
- 紙でもらった領収書 → 紙で保管(スキャンは可。ただし要件が複雑)
- メール等で受け取ったデータ → 電子のまま保管(検索・再現性が必須)
電子保存での注意点:
- ファイル名に日付や内容を記載(例:2024-04-01_打ち合わせ_交通費.pdf)
- スキャンする場合は両面・複数ページも忘れずに
- 電子データは検索可能な状態で保管
将来的には税務調査も電子化が進み、ファイル内のデータを絞り込んでチェックされる時代になると言われています。
3. 保管ミスのリスクとは?
仮に領収書が見つからなければ、経費として否認されるリスクがあります。さらに、ペナルティとして加算税や延滞税が発生する可能性も。
「まあこのくらいなら大丈夫」と思っても、いざ税務調査が入れば厳密な確認がされます。信頼される事業者であるためにも、正しい保管ルールの実践が重要です。
4. 効率的な保管のコツ
- 形式は「もらった形式のまま」が基本
- 紙は紙で、データはデータで
- 紙は紙で、データはデータで
- 自分にとって使いやすい方法で管理
- クリアファイルでも、クラウドでもOK
- クリアファイルでも、クラウドでもOK
業務効率の観点からも、正しく整理されていると経費精算や確定申告がスムーズになります。
5. まとめ
- 領収書は 原則7年、赤字年度は10年保管
- 電子帳簿保存法に対応し、形式に応じた保管を心がけましょう
- データは検索・再現可能な形で保管
- 正しい管理が税務リスクを減らし、信頼にもつながる
地味なようでとても大事な「領収書の整理と保管」。
今一度、社内のルールや運用を見直してみてはいかがでしょうか?
KUMA Partnersでは、フリーランスやスモールビジネスの実務を支える
「経理まわりの整備」について、実践的なアドバイスを提供しています。
お気軽にご相談ください。