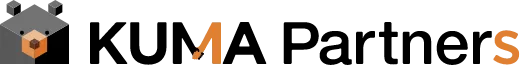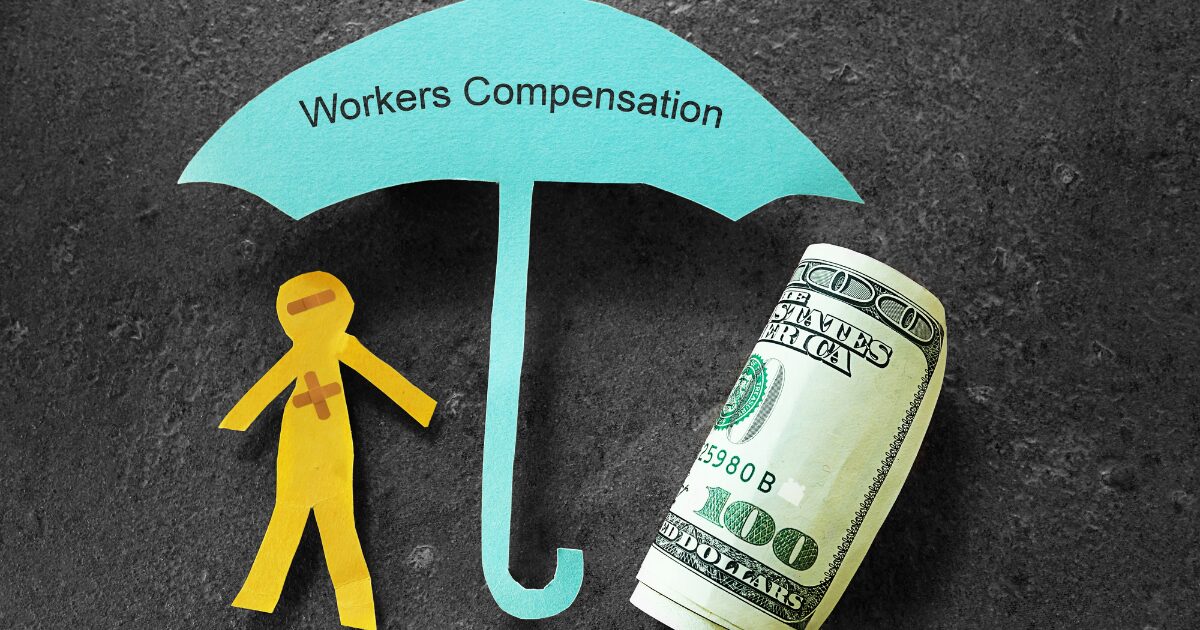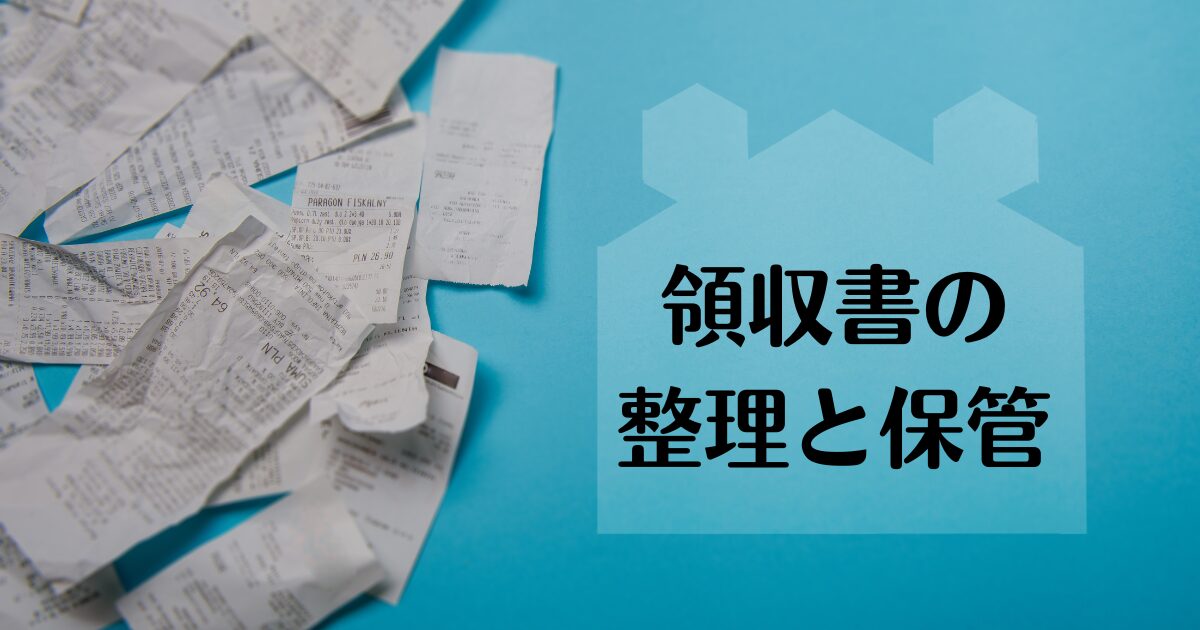役員報酬の最適化、できていますか?

社長のための「役員報酬」の基本
今回は、社長にとって非常に重要な「役員報酬」についてわかりやすく解説します。事業を成長させるうえで、会社の利益をどう社長個人の収入に変えるか。この“橋渡し”の考え方が、実はとても大切なのです。
そもそも役員報酬とは?
会社がどれだけ利益を出しても、そのお金はあくまで“会社のもの”。社長個人のお金ではありません。社長が自由に会社のお金を引き出して、自由に散財していいかというとそれは違法行為になってしまいます。
そこで必要になるのが「役員報酬」。会社から社長へ、正規の給与として支払うことで、会社の利益を社長個人の収入へとつなげる仕組みです。役員報酬は、会社側から見れば「経費」となり、法人税の対象から除外できます。一方、受け取る社長にとっては「給与」として扱われ、給与所得控除の恩恵も受けられるというメリットがあります。
所得税の仕組みを理解しよう
役員報酬をいくらにするかを考える前に、まず個人に課される「所得税」の仕組みを知っておきましょう。
日本の所得税は「超過累進課税制度」を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上がっていきます。たとえば、所得が195万円までは5%、そこから330万円までは10%、といったように段階的に税率が上がり、最高で45%にまで達します。
ここで勘違いしがちなのが「年収1,000万円の人は、全額に対して33%の税率がかかる」と思ってしまうこと。実際には、195万円までは5%、次の帯域は10%、というように分割して課税されるため、実効税率(平均的な税負担率)は20数%程度におさまることが多いのです。
法人税とのバランスが重要
一方、法人税率は個人とは異なり、ほぼ一定です。おおよそ20%台後半から30%台前半が一般的です。
つまり、個人の所得税率が法人税率を超えない範囲で役員報酬を設定することが、最も合理的かつ節税にもつながる方策となります。
たとえば、会社に1億円の利益が出た場合、このままでは約3,000万円の法人税が発生します。しかし、仮に5,000万円を役員報酬として社長個人に支払えば、その分会社の利益は減り法人税も抑えられます。
ただし、個人の年収が高くなりすぎると、所得税率が法人税率を超えてしまい、かえって税負担が増えてしまう場合も。ですので、目安としては年収1,000万円〜2,000万円の範囲で役員報酬を設定するのがひとつの基準です。
もちろん生活費など現実的な支出も加味して、適切な金額を見極めていくことが重要です。
まとめ:税率の違いを活かして最適化を
- 役員報酬は、会社にとっては経費、社長にとっては給与。
- 所得税は段階的に上昇する累進課税、法人税は比較的フラット。
- 個人の税率が法人税率を超えない範囲で報酬を調整することが節税のポイント。
税金の仕組みを理解することで、お金の残り方が変わります。ご自身の会社に合った役員報酬の設計を、ぜひ一度シミュレーションしてみてください。
ご不明な点や、より詳しく知りたいことがあれば、KUMA Partnersまでお気軽にご相談ください。