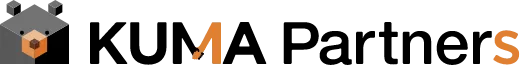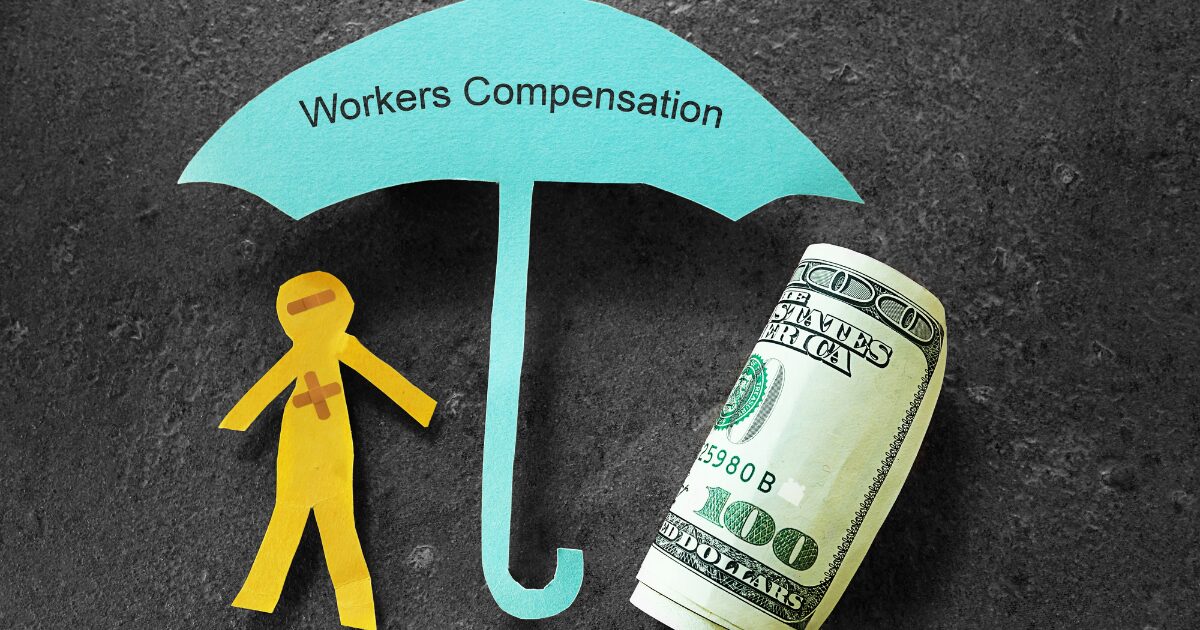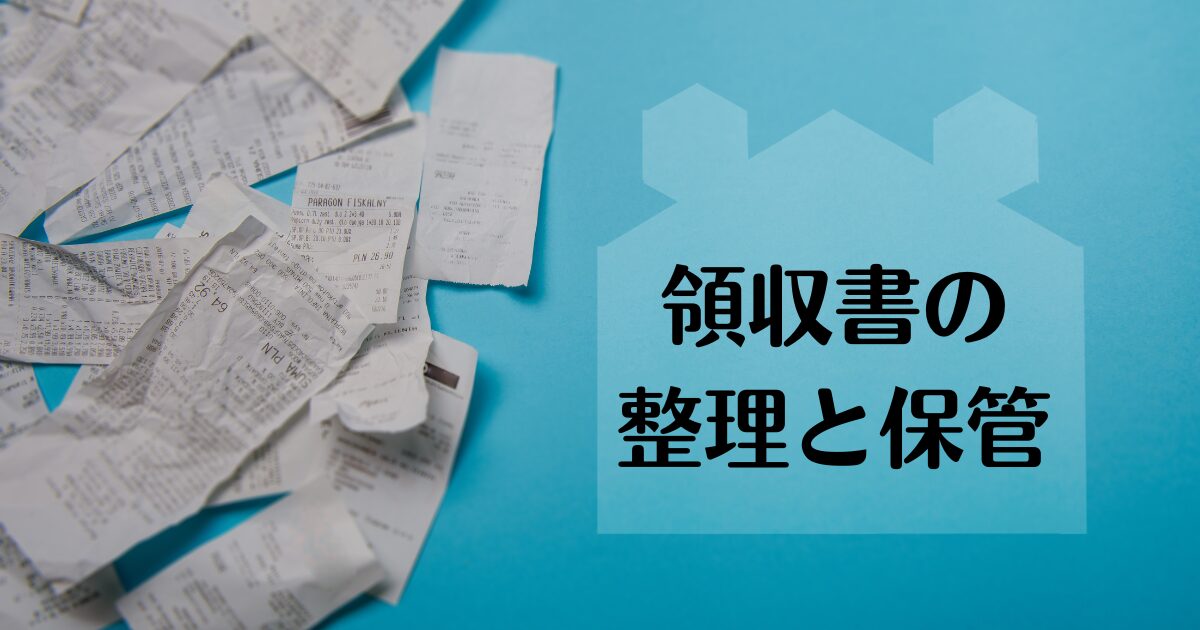消費税って結局なに?
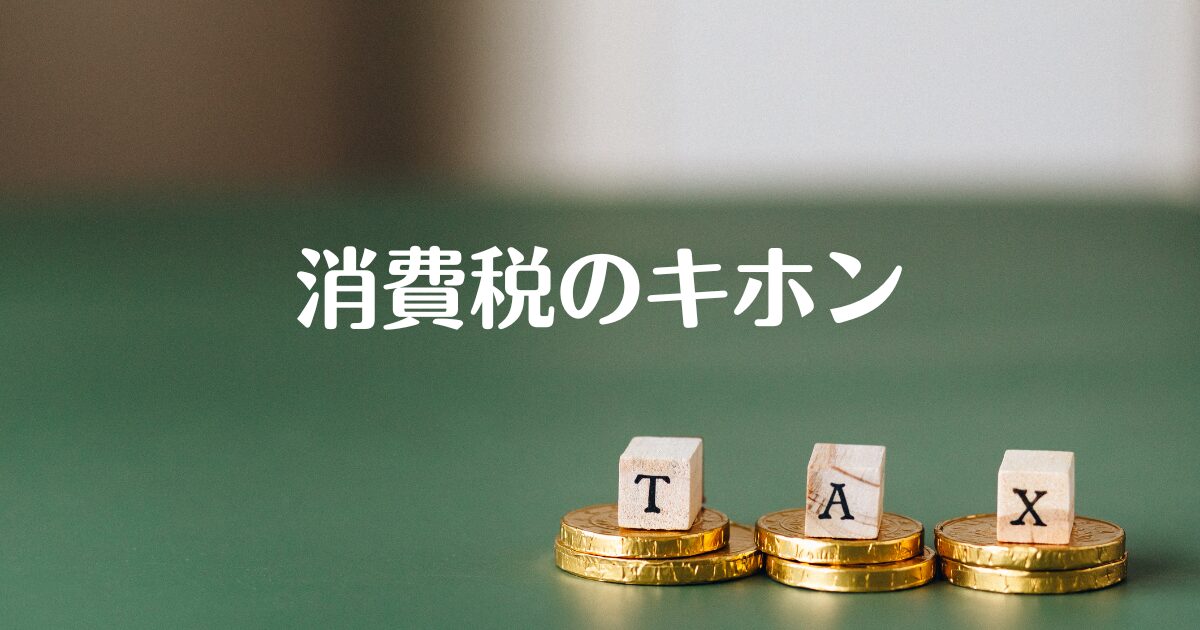
~事業者が知っておきたい基本と最新制度のポイント~
今回は「消費税」をテーマに、事業者の方が押さえておきたい基本的な仕組みから、最近話題のインボイス制度まで、わかりやすく解説していきます。
消費税の仕組みをおさらい
消費税は、商品やサービスの販売時に上乗せされる税金です。
たとえば、700円で仕入れた商品を1,000円で販売した場合、
- 仕入れ時に支払う消費税:70円(700円 × 10%)
- 売上時に預かる消費税:100円(1,000円 × 10%)
となります。
このとき、納税額は「預かった消費税100円 – 支払った消費税70円 = 差額の30円」です。
つまり、消費税は預かった額と支払った額の差額を納める仕組みなのです。
免税事業者ってなに?
ところが、この仕組みがそのまま適用されない「免税事業者」という制度があります。
たとえば、開業から2年以内の方や、2年前の売上が1,000万円未満の方は、「免税事業者」として申告することで、消費税の納税を免れることが可能です。
上記の例でいえば、消費税の30円を納める必要がなく、そのまま手元に残してよいことになります。
これだけ聞くと「お得」ですが、いくつか注意点があります。
注意点1:仕入税額控除が使えない
免税事業者は、「仕入れ時に支払った消費税」を税務上取り戻すこと(仕入税額控除)ができません。
たとえば、設備投資や不動産購入で支払いが多い年には、支払った消費税の方が多くなる可能性があります。
その場合、課税事業者であれば還付が受けられますが、免税事業者ではそれができません。
→ 設備投資を予定している年には、たとえ免税要件を満たしていても
「課税事業者になる」方がメリットが大きい場合もあります。
注意点2:インボイス制度による影響
2023年10月からスタートした「インボイス制度」では、インボイス(適格請求書)を発行するには課税事業者である必要があります。
つまり、免税事業者のままだとインボイスが発行できず、取引先が消費税控除できなくなるため、取引を敬遠される可能性があります。
「インボイス発行してますか?」という会話も増えてきました。取引先との関係性を維持するためにも、インボイス登録の有無は大きな判断材料となります。
結論:状況に応じて、最適な選択を
免税事業者になるか、課税事業者を選択するかは、
- 自社の売上規模
- 設備投資の予定
- インボイス発行の必要性
などをふまえて、毎年検討することが重要です。
消費税は「払うかどうか」だけでなく、「選択と戦略」が問われる時代に入っています。
ご不明な点や「うちの場合はどうなる?」といったご相談があれば、KUMA Partnersまでお気軽にお問い合わせください。