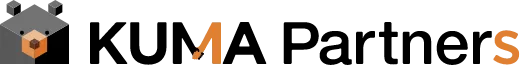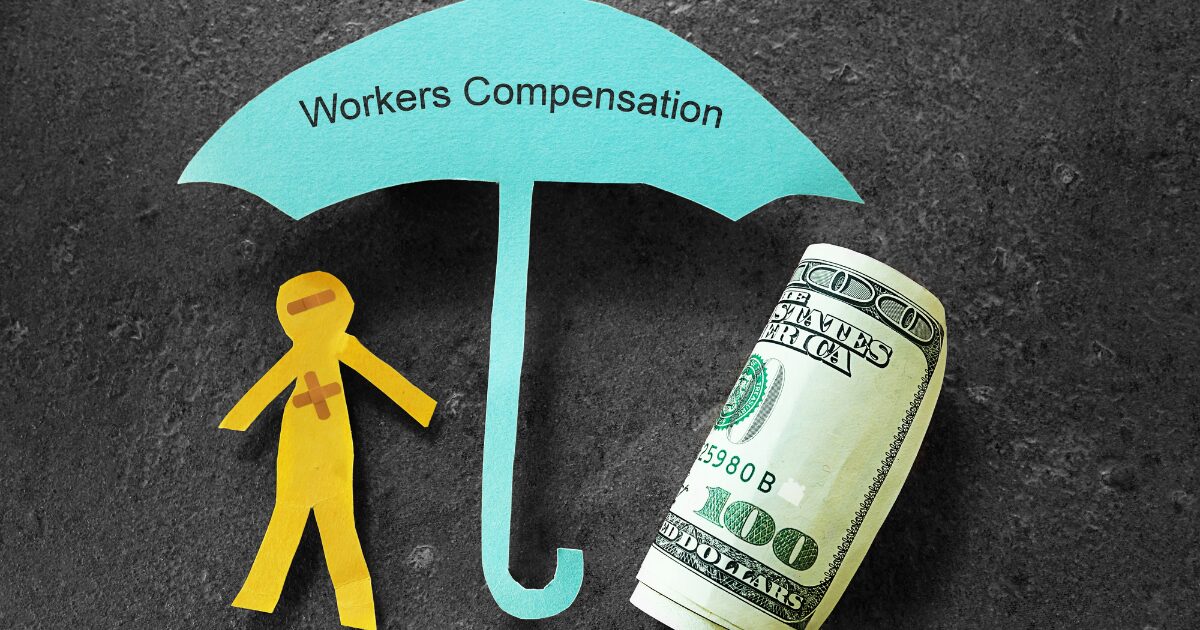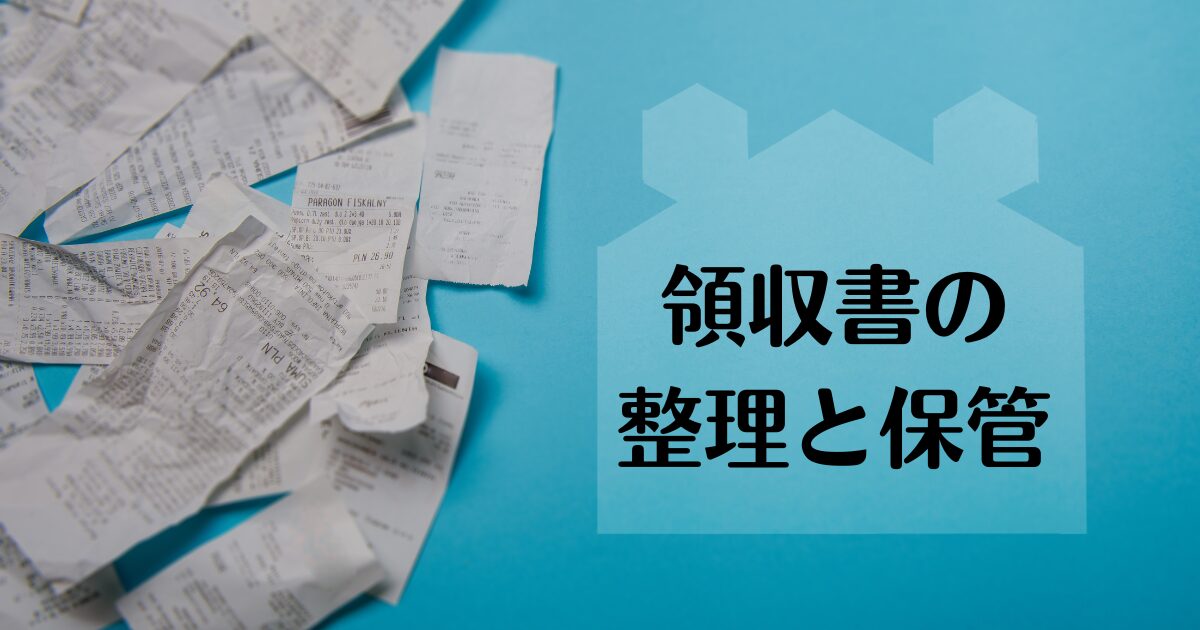福利厚生費をうまく活用するには?

こんにちは。
今回は、経営者の皆さまにぜひ知っておいていただきたい「福利厚生費の活用」について解説します。
「福利厚生費」と聞くと、大企業のイメージがあるかもしれませんが、実は中小企業や個人事業主でもうまく活用することで、従業員の満足度アップと節税の両方を実現できる可能性があります。
目次
そもそも「福利厚生費」とは?
福利厚生費とは、会社が従業員のために使う費用のこと。
たとえば、社員旅行や健康診断、ランチ代の補助、部活動の費用などが代表的です。
こうした支出は、従業員のモチベーション向上につながるだけでなく、一定の条件を満たせば会社の「経費」として計上することができ、結果として節税にもなります。
経費として認められるための3つのポイント
ただし、どんな支出でも福利厚生費として認められるわけではありません。ポイントは以下の3点です。
1. 「全社員が対象」になっていること
一部の社員だけが利用できる制度やイベントはNG。
「誰でも使える制度」として設計されている必要があります。
たとえば、社員旅行を行う場合、全社員に案内を出し、参加できる状態にしておくことが大前提。その上で、実際に半数以上が参加していれば経費として認められる可能性が高いです。
2. 制度やルールを「明文化」すること
たとえば「ランチ補助が1日○○円まで」「社員旅行は年1回、上限○万円」など、明確なルールを設けて、就業規則や社内規定に記載しておくことが重要です。
税務調査の際には、「規定を見せてください」と言われることも。社員に送ったメールや社内通達も、場合によっては証拠になります。
3. 公平性があること
特定の社員だけが得をしているように見える制度はアウト。
たとえば「社長がゴルフ好きだからゴルフ部だけ支援」ではなく、誰でも入れる部活制度にするなど、平等性と透明性がある設計が求められます。
注意点:目的は「節税」ではない
大切なのは、「福利厚生費は節税のために使う制度ではない」ということ。
本来の目的は、従業員が安心して、いきいきと働ける環境を整えることです。
その結果として、定着率が上がったり、生産性が上がったりして、会社の業績が良くなる——。そうした好循環を生むための投資が、福利厚生費なのです。
まとめ:ポイントは「公平な制度設計」
福利厚生費を活用する上でのポイントを、改めて整理します。
- 全従業員が対象になる制度であること
- 具体的なルールや規定を明文化しておくこと
- 公平性が担保されていること
- 税務調査を意識して、証拠をしっかり残しておくこと
これらを押さえておけば、モチベーションアップと節税を両立できる「おいしい制度」になります。
「制度設計に悩んでいる」「具体的にどうすればいいの?」といったご相談も、KUMA Partnersでは随時受け付けています。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断については専門家へのご相談をおすすめします。